最近の更新は下記がメインです。
Twitter https://twitter.com/ossam
Facebook http://www.facebook.com/osamuise
note https://note.com/ossam
最近の更新は下記がメインです。
Twitter https://twitter.com/ossam
Facebook http://www.facebook.com/osamuise
note https://note.com/ossam
こちらをよろしくお願いいたします!
久々の更新となりましたが、ここ最近はYoutubeを始め、インターネット、とくにスマホで見る動画コンテンツと視聴スタイルについて実験を繰り返しています。メディアづくりと、コンテンツづくりについて、最近おもしろかった本を5冊紹介します。
経営者は好きじゃないけど、 一番共感できるのはドワンゴの川上さん。コンテンツと、その配信と、コミュニティと、お祭りが一緒になったような。鋭い視点が満載。
例えば、UGC(コンシューマージェネレ−テッドコンテンツ)はオープンであるからコンテンツの画一化が起こる、とか。一歩踏み込んで世の中で言われていることはほんとなのか?を考えることの大事さに気付かされる。
HIKAKINさんとUUUMの鎌田さんの共著。ちゃんと読むと、本質的なことが書いてあります。視聴習慣を付けることとかはコンテンツづくりでとても大事ですね。テレビが毎日、毎週番組をやっているのと同じようなイメージを持ちました。
メディア視点でも、特にスマホメディアの場合、なんでKPIをMAUじゃなくてDAUにするのか、なんて議論があるけど、生活のペースに入り込むことを考えたら、WAUで見てるサービスは生き残れないんじゃないかな、なんて思わされます。(サービスの規模と哲学によるけど)
これすごくいいんですよ。ナタリーの運営スタイルや、哲学みたいなものがすごくわかる。「報道的であること」に基づいた姿勢で編集部が動いてることとか、ネットのメディアではなかったこと。一方で、編集部の押し付けじゃなくて、見るものはユーザーが選ぶ、というやりかたはインターネット的。時間をかけてしっかりコンテンツを作っていこう、という志をもっている方に勇気を与えてくれるのではないでしょうか。

ジェット☆ダイスケさんの本。3ヶ月前に読んだときは全然ピンと来なかったんだけど、すこしやり始めてみると深さがわかる。ただ、Youtubeで食べていくことはホントにラクではないけど、やりきったらいけるのも事実だと思う。好きなことで食べていくのは、楽しいことでもあるけど、覚悟のいることだと思う。だって、食べていけなかったら嫌いになっちゃうかもしれないから。僕は趣味を仕事にするタイプだけど、そうじゃない方は楽しみながらやるのが一番いいんじゃないでしょうか。

元日テレのガースーこと菅さんの本。プロデューサーは、ディレクターの演出に口を出さないこと、とか彼なりの美学が詰まってる。WEBでモノを作ってると、経営者がプロダクトを見てたりとか分業しなことによるメリットもあるけど、やっぱりプロデューサーは企画やキャスティング、お金周りなどクリエイターがものづくりできる環境を整えることに徹するのがいいかな、とは思ってる。映画が監督のものであるように、テレビ番組も演出のもの。
株式会社まさかでは、コンテンツとメディアの真ん中でインターネット動画事業を一緒につくり上げる人を募集してます。デザイナーや映像クリエイター、編集者、ライターで興味を持った方はぜひ。
イセオサム

先日見た舞台『鴎外の怪談(脚本・演出:永井愛)』が、Googleによるインターネット上の思想の支配(彼らは情報の整理とよんでいるのだけれど)と重なってなんともヤキモキしたので、一筆書いてみることにする。
明治期の軍医であり作家でもある森鴎外の苦悩を描いた作品。彼が思想弾圧の象徴であった大逆事件に遭遇した際、自分の置かれている保守的な立場である軍医と、自由な作家という立場の両極で苦悩するという内容。この時代には、海外から様々な思想が入ってきた。その際に、都合が悪い書物などを政府が発禁にし、弾圧していた。そして、書物のみならず、人や団体までもを逮捕し、死刑にするという大逆事件が起こる。その中で作家たちは、作品の中でメタファーを用いるなどして政府を批判し たり、新しい思想を伝えていこうとした。
たり、新しい思想を伝えていこうとした。
※大逆事件(1910年)では社会主義、無政府主義者を謳う幸徳秋水らが逮捕され、死刑に処された。裁判の中身はブラックボックス化しているが、政府による思想と言論の弾圧と言われている。
僕がインターネット上にブログというメディアで初めて何かを発信したのは10年と少し前の2003年だと思う。これまで、限られた人しか情報を発信することはないと考えていたので、なんて自由な場所ができたんだろうと感じた記憶がある。しかし近年、メディアをスケールさせ、事業にするにあたって立ちはばかる壁の存在が日に日に大きくなっていることに気がついた。GoogleやAppleなど巨人の存在である。
例えば、Googleの検索エンジンにとって都合の良いコンテンツ内容、構造にしなければトラフィックが回ってこない状況。Googleがよしとする思想や、SEOに最適化して記事のタイトルを書くなんぞつまらないことはやりたくないライターも多いのではないだろうか。
例えば、GoogleのAdsenseという広告ネットワークの掲載基準を満たした記事でないと収益を得ることは難しい状況。現状、過激な思想やビジュアルを含むコンテンツにおいて、広告を掲載することは認められていない。もちろん、Googleの広告を利用しなければよいという話であるが、マーケットのかなりの量を抑えているAdsenseを選択肢から外すことは難しい。
例えば、スマートフォンでアプリを配信しようとすると、Google PlayかAppleのApp Storeにコンテンツを提供しなければならない。サービスには審査があり、世界にサービスを配信しようとしたとき、この2つのネイティブアプリのマーケットを外して考えることはあり得ない。もちろん、それほどメリットがあるということの裏返しであるが、彼らがNGと言ったコンテンツは配信できない。僕らも、何本もお蔵入りのサービスを見てきた。
例えば、動画を配信する際は、自社でサーバーを持つことも可能だが、ファーストチョイスはやはりGoogleのYoutubeになるだろう。ここでも、彼らの基準を満たしたコンテンツのみしか配信は認められない。
など、日常で非常に便利なサービスも、別の視点から見ると不自由さを感じることがある。
これらを使わずとも表現をする方法はあるのだが、自由なはずのインターネットで影響力を持とうとすればするほど、どうもこの2社の気に入るコンテンツにせざるを得ない状況が存在する。現状では、多くのサービスにおいて事業の入り口も出口もGoogleやAppleのプラットフォームが絡んでおり、彼らにとって都合の悪いコンテンツを流通させることは難しいからである。(この2社に限らず、便利なサービスを提供してくれる巨人たちに感謝するとともに、それだけでは新しいコンテンツが生まれにくくなる、という危機感を感じている)
そこで今、一つの流れとしてGoogleからの脱却である。
トラフィックは機械である検索エンジンに頼らず、固定ファンと、ソーシャルメディアによる人力の拡散を得る。例えば「バイラルメディア」と言われるBuzzfeedやUpworthyなどは、Facebookからの流入が70%以上と言われているように、WEB上で新たな情報伝播の経路を得ている。(ここではFacebookやtwitterの存在はプラットフォームではなく、人力の集合体と捉えてみる)
収益は、一定基準を満たした広告主の集合体にすぎないアドネットワークに頼らず、広告主ごとにカスタマイズした、コンテンツ型の広告を制作する。(正確には、超テクノロジーの部分と、超人力なクリエイティブの両極を組み合わせる)また、課金する場合は、GoogleやAppleの決済ではなく、ダイレクトな課金方法を利用するのも手法として可能である。
など。上記は一例で、既存の施策とのミックスになるが、僕らは、僕らの思想をもって自由にメディアを運営できるように自活力をつける必要があるのではないだろうか。GoogleやAppleからアプリをリジェクトされたらサービス終了、という事業モデルではリスクが大きすぎると考えている。そのために、僕らがもつ面にこだわらず、コンテンツ配信の方法を多様化することで、クリエイターにメリットが提供できるかもしれない。
極論、僕らがメディアという「面」を持たずしても、コンテンツをあらゆるところに伝播させることができたら理想と言えるのではないか。SmartNewsの藤村さんも、“バイラル”の次にくるもの/「分散型 BuzzFeed」構想の衝撃というエントリで、情報やコンテンツが世の中に広がれば、自社にトラフィックを持ってくる必要性は必ずしもないのではないか、と述べている。そのために、ディストリビューション手段、運営手段としてGoogleやtwitter、Facebook、Instagram、LINEなどのプラットフォームと組めるところは組んでいくし、そうでない部分は自力で切り開かなければならない。メディアという「面」へのこだわりと制約を捨てることで、情報とコンテンツを配信する手段は無限に広がるのではないか。同様に、広告もネイティブ化し、コンテンツと同様に「面」ではない手段で広がっていく、という姿に形を変える可能性がある。
特定のプレイヤーに用意された土俵の上で戦うのは、少々飽きてきた、というのが最近思うことであります。だから、もっと自由なコンテンツ制作、配信、収益化の方法を構築していきたいと考えています。明治期の鴎外たちがそれを模索したように。
それではまた。
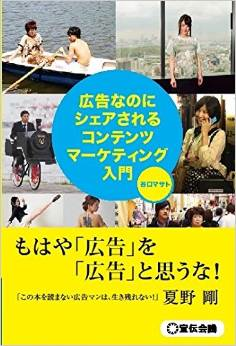
この3年間くらい、スマホでサービスを提供するにあたり、「シェアされるコンテンツとはなにか?」という課題に取り組んできた。ボタンをでっかくするなんていう技もあるけど、もっと本質的なコンテンツのつくり方、見せ方について。

※注:上記はよくあるでっかいシェアボタン。押せません。
僕の関わっている会社は資金調達しているわけではないし、そんなにお金がないので無料でプロモーション=シェアしてもらう必要があったからだが、いわゆるグロースハックの話をするときにもこのシェア(リファラル)の考えは欠かせない。
シェアには、コンテンツの尺、テキスト・画像・動画などのフォーマット、インセンティブの有無、サイトやアプリの導線、コンテンツに触れるストーリーなど複数の要素があるが、LINEの谷口Pが「シェアされるために必要なのは違和感、共感、満足感」と本に書いていて妙に納得してしまったので振り返ってみようと思う。
2011年に日本でのリワードメディアブームの走りとなったアプリを創った時には、ギフトカードに交換可能なポイントというインセンティブを付与することで、大量のシェアを発生させることができた。シェアすることで友達を誘える仕組みにより、twitterやfacebookにとどまらず、YoutubeやAppstoreまで大量のシェアが波及していった。これは、まあわかりやすいお金で人が動く事例。
また、友人がやっていた写真で一言ボケて(bokete)のアプリをプロデュースさせてもらったときは、いかにショートなコンテンツに破壊力をもたせるか、を意識して設計した。「写真で一言」は、パッと見て3秒で笑いを起こすことができる。笑いの感情が閾値を超えることで、自分の中では収まりきれず、友達に伝えざるをえなくなったのかもしれない。ここでは、twitter、facebookに加え、LINEが伸びてきたことがシェアを後押ししてくれたように思える。こちらは、違和感、共感、満足感が超短時間で起こる事例と言えそう。
2013年の後半になって、facebookを中心にシェアされるコンテンツボリュームに変化が現れたように感じた。これまで3秒で笑えるボケてや、面白画像などが単発でシェアされてきたのだが、1-3分くらいでみる読み物や、より感動を呼ぶストーリーがタイムラインに上がってくるようになった。もちろん、facebookの仕様の変更で、画像だけでなく、リンクのシェアが活きる時代になってきたのも要因だと思う。
というわけで、2014年に入ってからは新たにViRATESというニュースメディア・アプリをプロデュースしている。世界の面白ニュースや、提携パートナーの記事に加え、独自で制作する動画(第1弾公開中)や取材記事をこれから増やしていく予定だ。こちらはコンテンツボリュームが1-5分と、これまで手がけてきたサービスよりはちょっと長いので、なかなか作法に違いがあって面白い。記事に触れる瞬間から、シェアで出て行く瞬間までの流れのパターンが多く、分析しがいがありそう。

また、最近では「ご当地バカ百景」というアプリをLINEで広告プロデューサーをしている谷口さんや仲間たちと、個人活動として一緒に創らせて頂いた。
※谷口Pのブログより
後日、「ボケて」を運営しているオモロキ代表の鎌田武俊さんより連絡を頂き、「ゆーすけべーさんより、谷口という人は頭がおかしいので一度会った方が良いといわれたので、一度話でもしませんか」という事だった。
会って話をする中でふと、「個人活動でやってるバカ日本地図と、ご当地情報のサイトchakuwikiをアプリ化しようとして、一度サイバーエージェントの役員自らが審査するというアプリコンテストに出した事があるが、あっさり落ちた」という話をした。
すると、それは面白いから是非アプリ化するべきだと言われ、「ボケて」のアプリを開発したブレイブソフトの社長、菅澤英司さんと、プロデュースしたイセオサムさんを紹介してくれるという話になった。※オモロキさんはご紹介頂いたのみでアプリには直接関係していない。
谷口Pと話をする中で、シェアが起こるときのユーザーの気持ちについて、沢山の学びがあった。最近発売された彼の著作にもあったが、シェアされるために必要なのは「違和感、共感、満足感」らしい。例えば、タイトルやサムネイル画像における引っ掛かりで記事を読んでもらう。そして、内容に共感してもらう(もちろん面白いことが前提)。最後に、その記事に出会ったところから、タイトルとのギャップが無いこと(釣りじゃないこと)、面白さを含めて満足を得てもらうこと。この流れを高打率で生み出すことにプロフェッショナル性があるのではないだろうか。僕はこうとらえたのだが、人によって解釈が異なる部分があるかもしれない。
すごくいい本なので、シェアとコンテンツ、広告あたりに興味がある人はぜひ。
バイラルメディアが流行っている、とよく言われるけど、この仕組みがシェアを起こしやすいのは、facebookでシェアされてきた記事を、次の人にバトンを渡すようにシェアされるからだと思う。シェアしてつないでいくという、雪だるまの最初の部分ができた状態で回ってくるから、カンタンに次にバトンを渡せる。ALSのアイスバケツチャレンジもこの仕組みに近いのかもしれない。ただ、これがボケてとかの極端にショートなコンテンツだと意外にキツい。シェアの連鎖は起こりにくいから、サイトやアプリから、まだだれもシェアしてないボケを自らの判断でシェアすることになるからだ。facebookにシェアしていいねがつかなかったら、自分の笑いのセンスを疑われてしまうし。
というわけで、シェアって人にボールを渡すことだから、自分でシェアしたい気持ちと、他人のシェアされたい気持ちの間をつなげるとキレイに回るのかな、と思う。この「シェアされたい」という要望は企業からもよく頂くのだが、これからネイティブ広告を制作していくことが増えると思うので、boketeやViRATESで一緒にシェアされるコンテンツ・広告づくりをしたい方、コチラよりお声がけくださいませ。
違和感、共感、満足感とあるが、僕の記事は最後に満足感を与えることができたのだろうか。